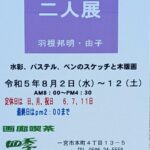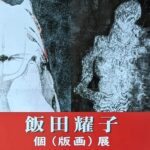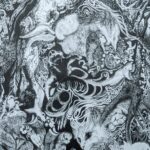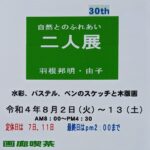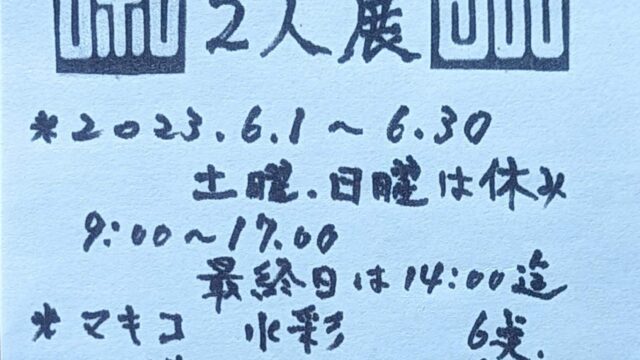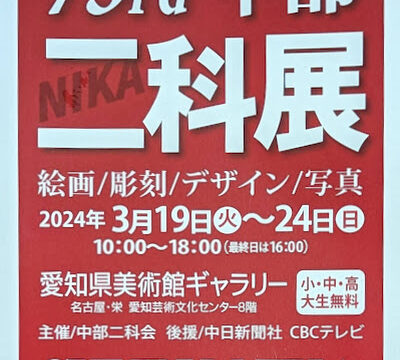・・・銅版画家として多くの根強いファンを持つ鈴木孝太朗氏。昨年大規模な遺作展が開催され大盛況でした。
遺作展では、同氏の代表作である日本の古代とナスカの地上絵をコラボした「アクアチントとエッチングの併用作品」が多くを占めました。
一方、同氏の【メゾチント作品】をもっと見たかったとの声も多くあり、奥様のご尽力によりこの度の展示会となりました。
この度のメゾチント作品主体の展示会を楽しんでいただき、気になった作品の記憶の一助になれば幸いです。
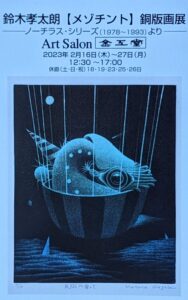 写真:鈴木孝太朗【メゾチント】案内状。
写真:鈴木孝太朗【メゾチント】案内状。鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画展
 写真(2023/2/16):金工堂(地下鉄栄2番出口)。
写真(2023/2/16):金工堂(地下鉄栄2番出口)。展示会場、Art Salon 金工堂
- 展示期間:2023/2/16(木)~27(月)。
- 開館時間:12:30~17:00。
- 休館日(土・日・祝):18・19・23・25・26日。
 写真(2023/2/16):鈴木孝太朗作品と奥様、Art Salon金工堂にて)。
写真(2023/2/16):鈴木孝太朗作品と奥様、Art Salon金工堂にて)。展示作品紹介
・・・今回は、主に1978年~95年制作の【メゾチント作品】を中心に展示してあります。
窓1.
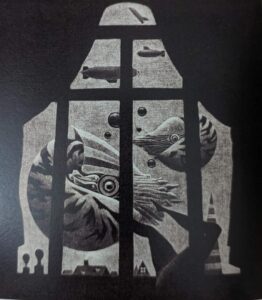 メゾチント:19.7×17.7mm
メゾチント:19.7×17.7mm
window1.
 メゾチント:19.7×17.7mm
メゾチント:19.7×17.7mm
’95・Nautilus・M・5
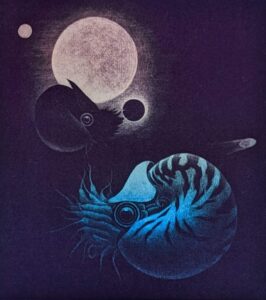 メゾチント:19.7×17.7mm
メゾチント:19.7×17.7mm
(no title)
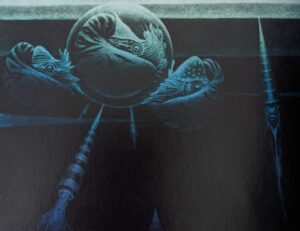 メゾチント:19.7×25.5mm
メゾチント:19.7×25.5mm
Nautilus・M・15
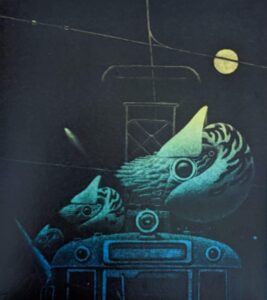 メゾチント:19.7×17.7mm
メゾチント:19.7×17.7mm
Nautilus・M・6
 メゾチント:19.7×17.7mm
メゾチント:19.7×17.7mm
work・M・14
 メゾチント:19.7×36.0mm
メゾチント:19.7×36.0mm
work・M・17
 メゾチント:20.0×36.2mm
メゾチント:20.0×36.2mm
気球に乗って Nautilus・MM・2
 メゾチント:14.8×11.8mm
メゾチント:14.8×11.8mm
(no title)
 メゾチント:9.8×36.2mm
メゾチント:9.8×36.2mm
on the B.B
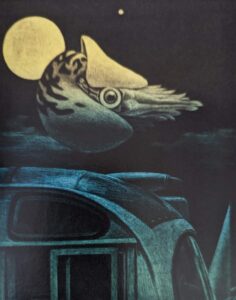 メゾチント:14.8×11.8mm
メゾチント:14.8×11.8mm
(no title)
 メゾチント:19.7×17.7mm
メゾチント:19.7×17.7mm
Nautilus・MM・4
 メゾチント:14.8×11.8mm
メゾチント:14.8×11.8mm
皆既日食 Nautilus・MM・3
 メゾチント:11.8×14.8mm
メゾチント:11.8×14.8mm
Nautilus・L・1
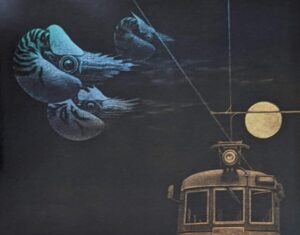 メゾチント:23.8×29.8mm
メゾチント:23.8×29.8mm
その他
・・・展示会場の一角に、【メゾチント】制作用の道具及びその説明パネルがあり、銅版画技法をご参考まで掲載しました。
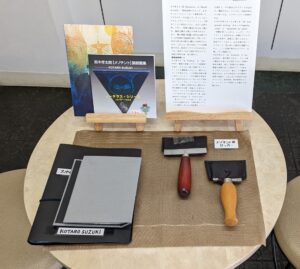 写真:(左上)鈴木孝太路作品集と【メゾチント】銅版画集、(右下)メゾチント用ロッカー。
写真:(左上)鈴木孝太路作品集と【メゾチント】銅版画集、(右下)メゾチント用ロッカー。メゾチント
技法
銅版など全体にわたって、先ずロッカー(ベルソー)という道具を用いて、小さなささくれを起こします。
そうしておいてから、スクレーバーとパニッシャーで明るくしたい部分をつぶし、あるいは削り取ってゆきます。
明暗の濃度がきわめて豊かな、微妙な調子を備えた手法であるが、また、最も慎重な配慮と根気を必要とします。
作家
近代英国の版画家が好んで用いましたが、日本人の長谷川潔、浜口陽三に優れた作例があります。
尚、これによく似た技法として点刻彫版があります。細身の小刀で小さな点を打ってゆく技法です。
英国で好まれましたが、石版の発明以後急に廃れました。
その他
Nautilus(ノーチラス)とは、オウムガイ・アオイガイの意味、同氏の作品に登場します。
一方、1800年にフランスで建造した潜航艇名、ラテン語で「小さな船」の意味もあります。
腐食銅版画
・・・エッチング、リフトグランド・エッチング(シュガーアクアチント)、アクアチントなどあります。
エッチング
銅板夫表面にグランド(防触剤)を塗り、その上から針で描画する。そしてこれを腐食駅にひたして、線のニュアンスを強化します。
この作業を何度か繰り返すことにより、一枚の銅板が完成します。16世紀初めから広く用いられた技術。
デューラー、レンブラント、ゴヤらに多くの優れた作例があります。
最近では、銅を腐食させる際、有毒ガスを発することからアルミニウム板が使用されます。
ソフトグランド・エッチング
柔らかいグランドを用いて、太い、おだやかな画面を作ります。牛脂を加えたグランドを敷き、
その上に物を置き、プレスを通すと、その部分だけグランドがはがれ、腐食されることになります。
18世紀の初めから用いられ、ミロやヘイターの作例があります。
リフトグランド・エッチング
砂糖を使うことから、シュガー・アクアチントとも呼ばれます。
砂糖とアラビアゴムの溶液で銅板上に描いた上から、液体グランドをひきます。
ぬるま湯の中につけておくと、先に描いた部分が遊離するから、
個々に松脂の粉末を振りかけ、定着してから製版します。
アクアチント
線の調子でなく、むしろ面の濃淡が主体となる技法です。銅板に松脂の粉末を撒き、熱して定着させます。
その銅板に腐食の強弱に応じて液体グランドを塗る事により、面としての濃淡が実現されます。
ゴヤの作品中には幻想的な背景の処理に、しばしばこの技法が多用されています。
浜田知明、駒井哲郎などによる優れた作例があります。(引用:展示会場、キャプション)。
鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画集
・・・今回の展示を機に奥様が、鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画集を発行されました。
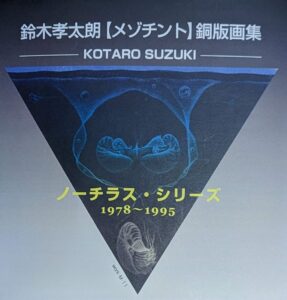
今回未展示の作品一部紹介
・・・鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画集を展示会場で頂戴しました。今回展示できなかった作品も一部紹介します。
Nautilus・M・3
 メゾチント:19.7×17.7mm
メゾチント:19.7×17.7mm
Nautilus・M・4
 メゾチント:17.8×19.8mm
メゾチント:17.8×19.8mm
(no title)
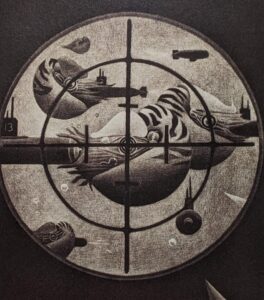 メゾチント:19.7×17.6mm
メゾチント:19.7×17.6mm
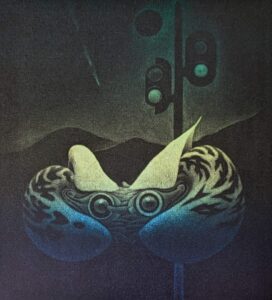 メゾチント:19.7×17.7mm
メゾチント:19.7×17.7mm
鈴木孝太朗【メゾチント】銅版画展のまとめ
・・・銅版画家として多くの根強いファンを持つ鈴木孝太朗氏。昨年の大盛況だった大規模な遺作展が思い出されます。
今回は、鈴木孝太朗氏が遺された数多くの作品の中から、メゾチント作品を選んだ展示でした。
まだ未整理の作品も多々お持ちのようです。またの機会に未公開の作品の展示が待たれます。
鈴木孝太朗氏の膨大な数の作品を目の当たりにし、同氏の銅板画に対する、真摯で精力的な制作意欲を感じます。
そして今日でも、銅版画を広めようと精力的に活動中でのご逝去を残念に思います。
短い期間でしたが、版画伍人展のメンバーとしてご一緒できたご縁と幸運に感謝し、
今後も同氏の作品の展示活動をフォローし記事にしたいと思います。
最後までご覧いただき有り難うございました。